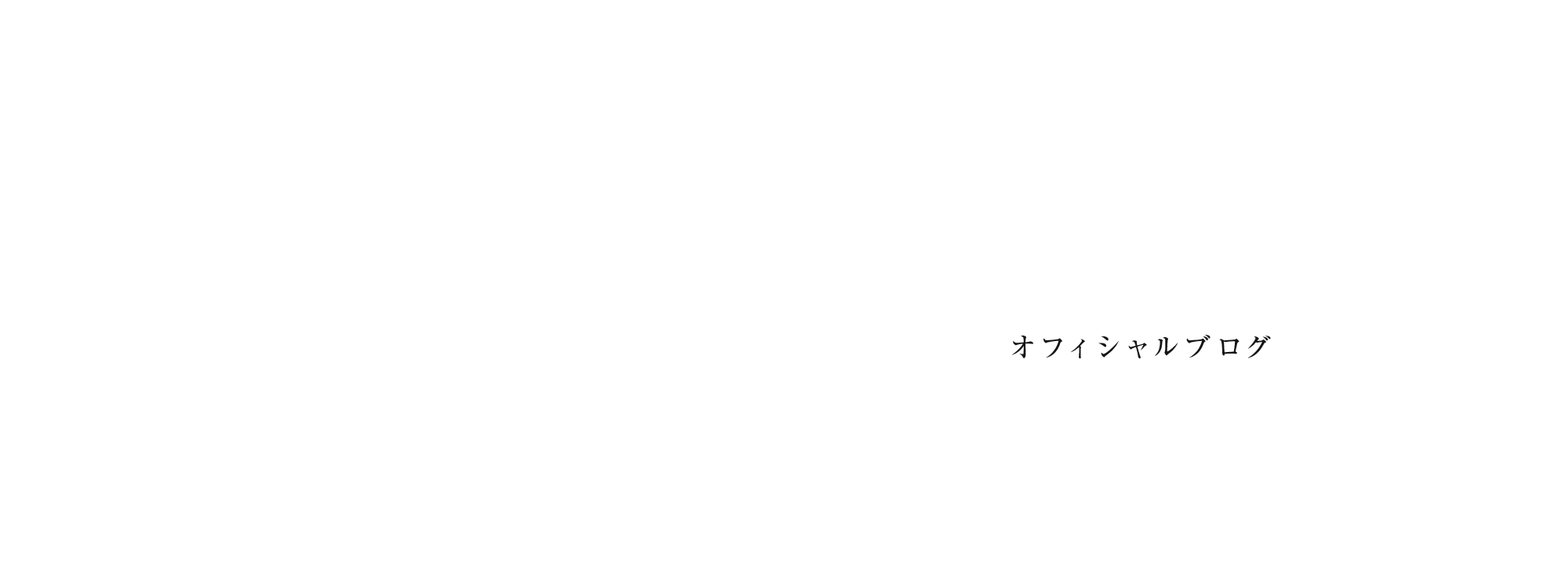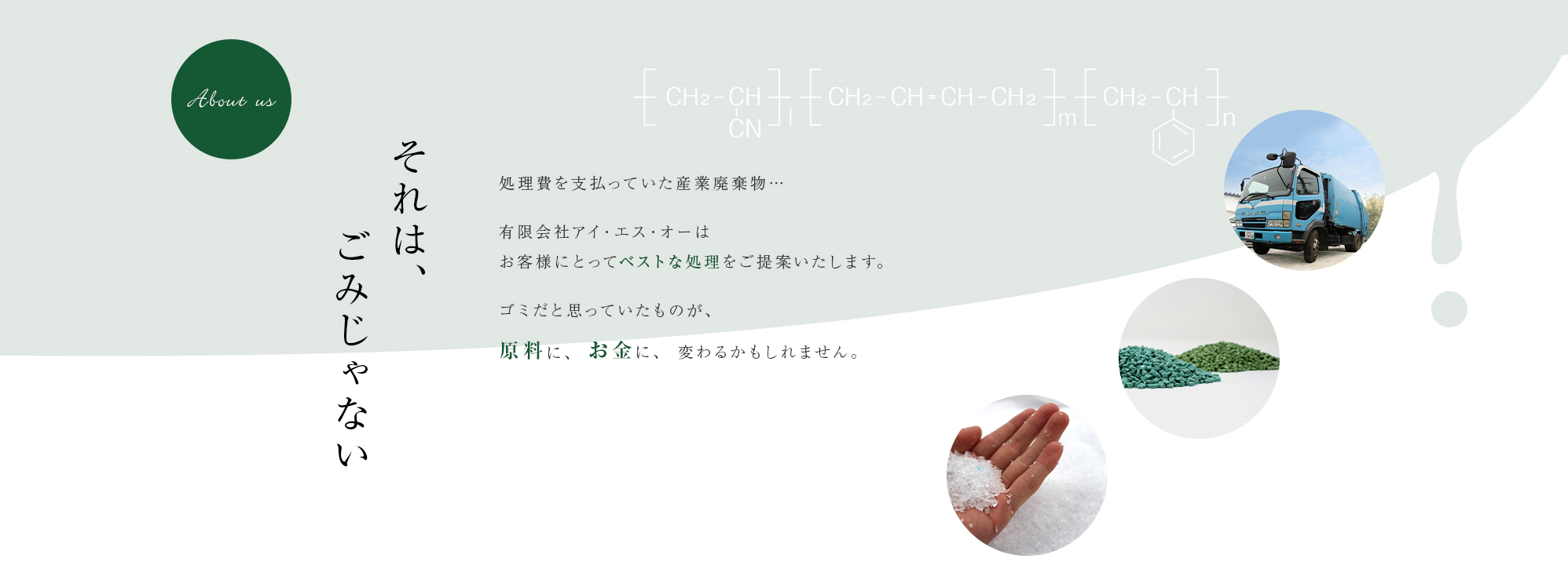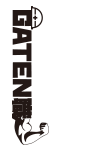春の季語「暖か」を使い、そこに生命を感じさせる蕊(しべ)が来たと思ったら、熱で溶ける蠟(ろう)が来て、造花という人工の花。
何とも芥川っぽい作品です。
1900年前後ですから紙や布に塗っているのかは分かりませんが、羅生門などを思うと、暗闇で蝋燭から筆で塗っているような、春とは違う暗さを感じてしまいます。
花の木に あらざらめども 咲きにけり
ふりにしこの身 なる時もがな (古今和歌集 445 文屋康秀) |
こちらは木(メドハギ)を削って作った削り花(造花)ですが、こちらも「私も役に立つ(実がなる)時がくればいいのに」と下の句が来ているように、自身の不遇を歌うと、、、なかなか上手い歌です。
冷たい風が入り混じるものの、日中は夏日がやってくるなど、暖かくなりました。外で作業していると暑すぎなくらいです。
ここから夏がやってくると思うと、ぞっとします。
防草シートが色んな場所で施工されているのを年々見かけるようになってきました。
草抜き草刈をして、家庭菜園や花壇を作って、、、といった作業も、この数年の酷暑で随分苦しくなったのではないでしょうか?
道路沿いにきれいに花を植えてあるところがあったのですが、一昨年くらいに防草シートが張られたと思ったら、昨年にはコンクリートが流し込まれていました。
花(植物)を愛でるというのは自然へ愛を向けていることになりますが、そのために猛暑日に草抜きするなど維持管理をするのは大変で、自然から苦難を向けられているような気にもなります。物価の上昇も花の苗だって御多分に漏れず2倍どころでない苗もあります。
桂離宮の枯山水とは別の動機で同様な成果物が出てきそうですね。
そこで、最初の句に戻ってくるわけです。
AR(拡張現実)など何を使うかはアイディア次第ですが、古きを想い、四季を再現する、、、
そもそも異常気象によって四季自体失われる未来がやってきて、現在の異常気象が以上でなくなるかもしれませんし、、、
最後までお読みいただき、ありがとうございました。