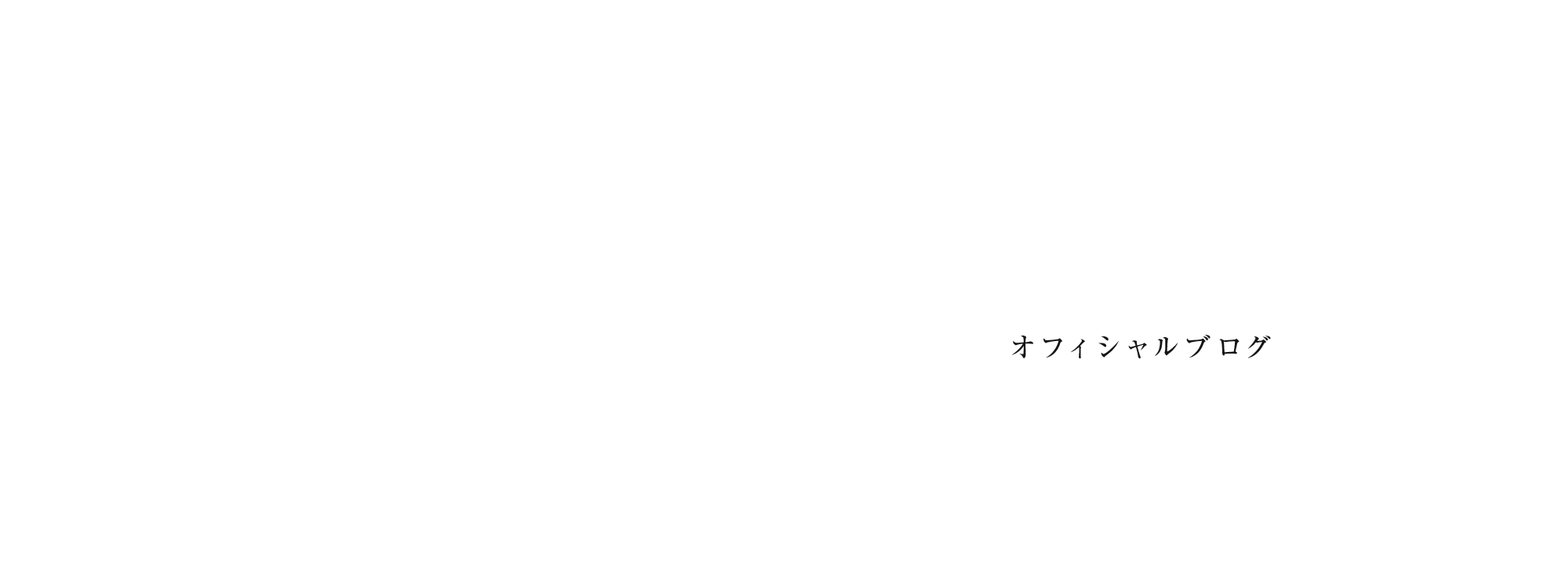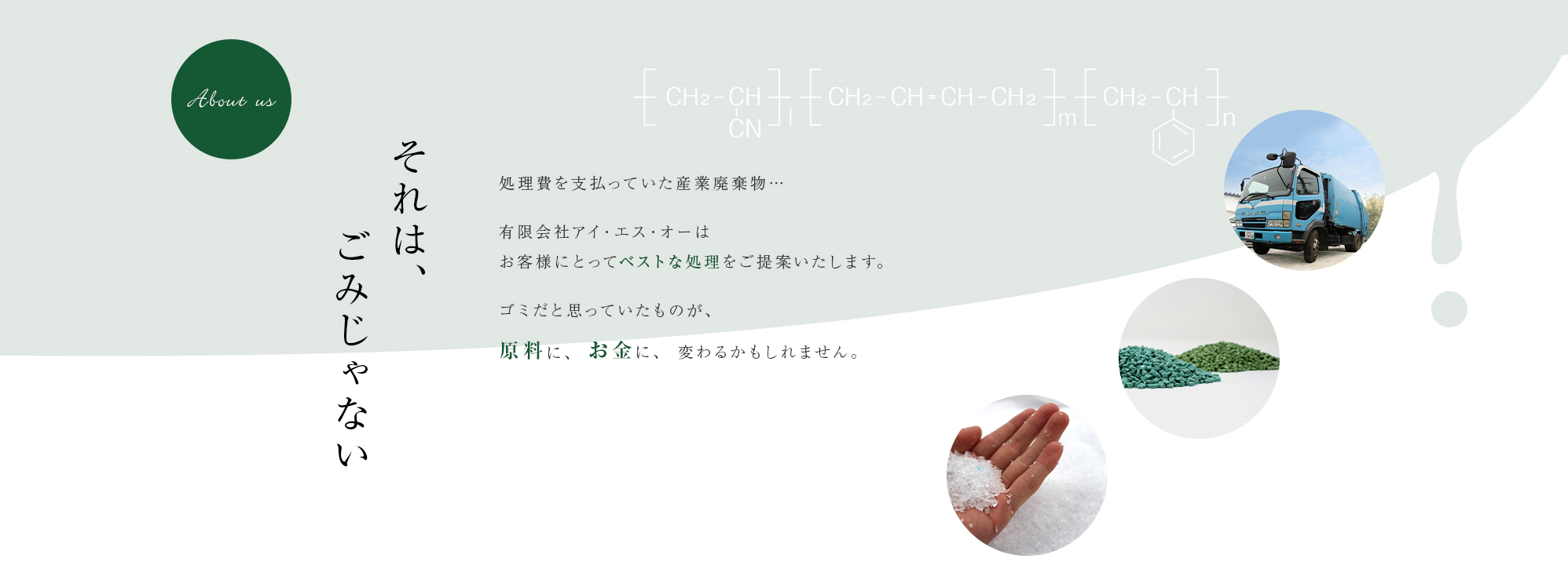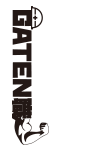片付いていて綺麗だという話ではなく、美しさについて話したいと思います。
日本人の美意識を語る時、川端康成『美しい日本の私 その序説』谷崎潤一郎『陰翳礼讃』が挙げられるでしょうか。
電気のない薄暗い室内と屏風の金色についての説明を読んだときは芸術作品の鑑賞動線や配置についてもっと注意を払わなくてはならない、すべてが芸術装置だと意識付けされました(蝋燭の灯りを想像するとファラデーの『ロウソクの科学』にも飛び火しそうですが)。美術館はそうしたものの最たるもので、美術館自体の建築家から知らなければとも思い、建築物にも関心を抱くようになりました。『金閣寺』ほど狂気さはありませんが、白井晟一作品が好きで長崎県にいったときは建物を見に行きました。
“狂気の”という形容詞を英語にしたとき”ルナティック(lunatic)”と訳すことができます。ルナはローマ神話の月の女神でラテン語の月に由来します。月の魅惑さに取り憑かれたんではないかと思える建築物に桂離宮の月波楼があります。月を鑑賞するために作られた構造をしている建物です。「月点波心一顆珠(月は波心に点じて 一顆の珠)」、池に映る月をも愛でることができるようで、風流さがあります。ムーンリバーという曲もありますね。『ティファニーで朝食を』のオードリーも美しいです。カポーティーの短編の技巧も美しいですかね。ムーンリバーとなると、ムンクの絵画も思い浮かびます。宮崎県は東側に海岸があるので、水平線からの月の出を見ることができます。日の出ばかり取り上げられますが、夜の水平線から月が昇ってくる様は美しいですよ(事前に月の出の時刻を調べないと、夜に見れません。私は満月で夜に月の出が起こる日を調べて見に行きました。年に何回とないので見に行くのは意外と難しいです)。
と、延々と出てきます。
狂気の方向に向けると、アングラ的な美、こちらは心を動かされることと美しいと思うことを重ねる必要も多少あるかもしれません。この辺りは現代美術でも求められる美観かもしれません。
ただ、自然も必ず美しいとは限りません。
恐山や富士の樹海と聞くと、山や森なのに美しいとは思わないでしょう。
神木や境内の木々には美しさと畏れが同居します。欧州だと森に魔女が住んでいます。
西洋では自然は支配するもの、日本では自然は共存するものと説明した文章を書いたのは誰でしたでしょう?
ハイネ『流刑の神々』には「教会は古代の神々を(中略)今や地上の古い神殿の廃墟や魔法の森の暗闇のなかで暮らしをたてている悪霊たちであると考えている」とあります。それでも、イルミネーションは16世紀ルターが森の中で木々の間から星が見える光景を再現しようとしたのが始まりとあるように、森の中にいてもまやかしではなく美しいものは美しいと感じることはできたようです。聖職者であったことや美の対象が星であったことも無視できないでしょうが。
花田清輝『海について』には「海のうつくしさというようなものは、19世紀の発明にかかるものであって(中略)あの青い水も、白い波も、ブロンドの砂原も、灰いろや黄いろの岩も(中略)むしろ、恐怖すべきものとして、つとめて避けられてきたのだ」とあります。汎神論論争からのロマン主義、つまり(古典的)キリスト教を基盤にした世界が壊されたことで、”流刑の神々”の土着文化的自然愛が再発見されたということでしょう。
薄暗い森にお化けが住んでいると思えば不気味に見えるし、神様のようなものが宿っていると思えば美しく見えるわけです。これが屏風であるし、川端康成のスピーチにも現れるわけですね。
デュシャンが芸術とは新しいものの見方を創造することといった趣旨の発言をしていたと思うし、これらは正義を語る時にも同じ切り口で語れるわけですが、この情報が氾濫した世界で何を指針にどこへ向かえばいいのか悩むところではあります。
どこにいても何者であっても何かがしやすくなった世界であるとともに、このつかみどころのない世界は、気が付いたら溺れそうでもあります。
そういう点では私の場合、現在の仕事に根を張り続ける制約条件があることで、目的達成を最大化しやすいのかもしれません。
風呂敷の畳み方が分かりません。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
有限会社アイ・エス・オー 長友